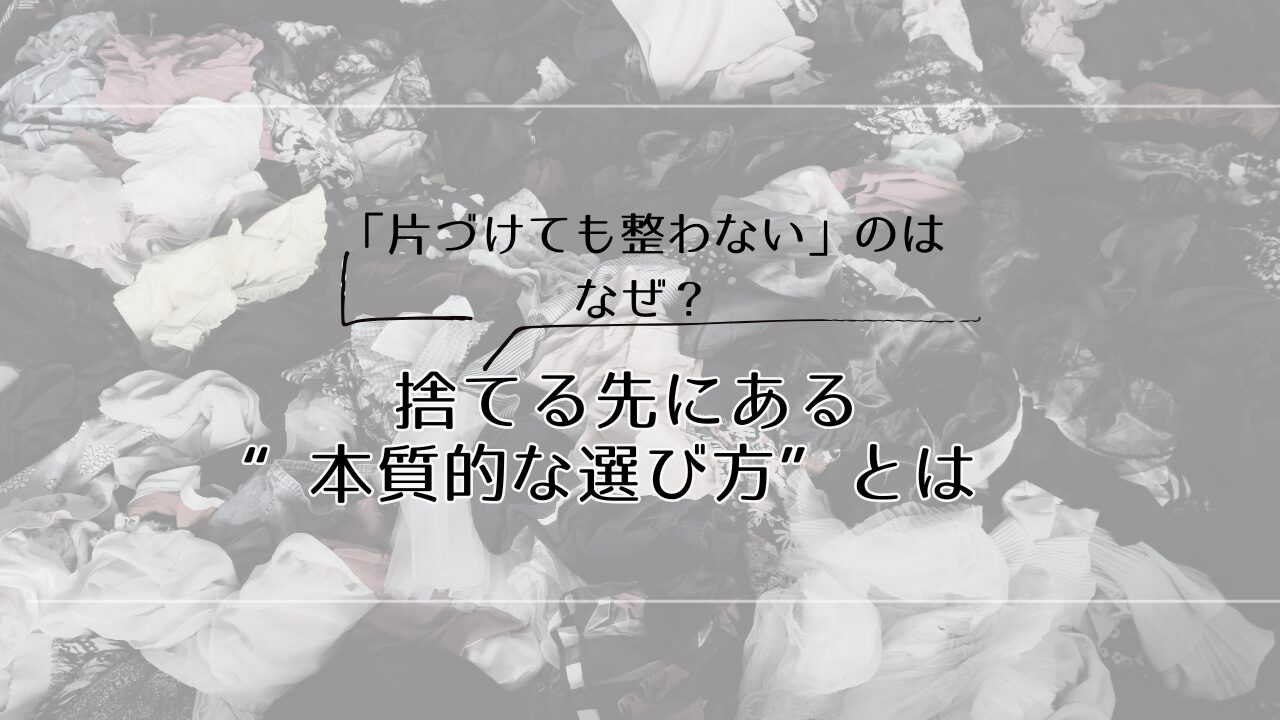
片づけ=捨てる、だけではない
「片づけ」と聞くと、多くの人がまず思い浮かべるのは
「捨てる」という行動かもしれません。
(狭義には使った物を元に戻すことが片づけですが、一般的には整理整頓収納片づけすべてを「片づけ」と捉えられている)
2000年代以降、「断捨離」や「ミニマリズム」といった、
“できるだけ物を持たない暮らし”を推奨する考え方が注目を集めました。
中には「手放した先にどう生きるか」を軸に据えた提案もありますが、
現実には、「捨てること」自体が目的化してしまっているケースも少なくありません。

買っては捨て、また買うサイクル
同じ頃、暮らしのあり方自体も大きく変化してきました。
ファストファッションや低価格帯の生活雑貨が普及し、
「安く手に入る」「また必要になったら買えばいい」といった考え方が一般的に。
さらにSNSやアフィリエイトの影響で、
商品を紹介することそのものが情報発信の一部となり、
“物を手放す”ことと“物を手に入れる”ことが、同じスピードで繰り返されるようになっています。
結果として、「捨てる」「買う」「また捨てる」というサイクルが、
無意識のうちに多くの人の暮らしに組み込まれているのです。
片づけの現場から見えた、もう一つの課題
暮らしを整えるサポートを行う中で、
私たちはこれまで数百の家庭で“物の見直し”に関わってきました。
リサイクルや寄付、資源回収など、次につながる手段を提案しながらも、
実際には、使える状態の服を1万枚以上手放す現場に立ち会ってきたという事実があります。
物も入れたら…数万…数えることができない量です。
ただ、その目的は「暮らしが滞ってしまっている状態を改善すること」でした。
不要な物を手放すことで、空間を確保し、動線を整え、気持ちを切り替える。
それは確かに必要なプロセスです。
しかし最近になって強く感じるのは、
“捨てる”という行為の先にあるはずの「変化」が、本当に起きているのか?という問いです。

忘れるから、また繰り返す
多くの人は、昨年何を捨てたかを覚えていません。
それは、視界から消えたものに対して意識が向かなくなる、人の認知の仕組みにも起因します。
記憶されていないからこそ、また同じような物を買い、使い、気づかないうちに手放す。
たとえ部屋がスッキリしても、
その物が生まれるまでにかかった資源やエネルギー、
捨てたあとの処理にかかる社会的コストまでは、目に見えません。
その“見えないもの”に無関心なまま、私たちは「スッキリした」という感覚だけをもとに、
消費行動を繰り返してしまうのです。
「使い切る」は、難しくて尊い選び方
一度手にしたものを、最後まで使い切る。
この行為こそが、最も持続可能で、誠実な「選び方」なのではないでしょうか。
例えば、文房具・化粧品・衣類など。
それぞれは“消耗品”という括りですが、
実際に「最後まで使い切ることができた」と胸を張れるものは、意外と少ないかもしれません。
「これ、本当に使い切れるだろうか?」
「最後まで、自分の手で見届けられるだろうか?」
そんな問いかけが、次の消費の入口でブレーキになる感覚。
それこそが、“選び方”の再構築につながる第一歩です。

「入口」を見直さないと、何度でも元に戻る
「もう買わない」「増やさない」といった禁止ルールは、
長期的に見ると大きなストレスになりやすく、現実的ではありません。
けれど「使い切ったら次を買おう」という小さなルールなら、
気持ちに余白を持ちながら、暮らし方を変えていくことができます。
その過程で、自分の持ち物に対する感情や、
「なぜ、こんなにも使い切れない物があるのか」という気づきが生まれます。
そこにあるのは、買い方・選び方に影響を与えている“自分の価値観”です。
どんなライフスタイルを送りたいのか。
何を「大切」と感じるのか。
どのように暮らし、社会に関わりたいのか。
それを自分自身で言葉にしていくことが、
物の持ち方、そして片づけの本質的な意味を変えていきます。
「片づけても整わない」のは、なぜ? 捨てる先にある“本質的な選び方”とはーまとめ
- 捨てることは「整える手段のひとつ」であって、目的ではない
- 本当に暮らしを変えるには、「入口=選び方」を見直すことが必要
- 「使い切れるか?」という問いが、新しい基準になる
- 使い切った時に、立ち止まって自分との関係性を見直す
- 自分の価値観を知ることが、持ち物にも暮らしにも影響を与える
これまでずっと「自分の」「暮らしを」「滞りなく、心地よく過ごせるようにする」ことをメインに、
減らすことの良さ、片づけるための考え方や手法を伝えることが多いコラムでしたが、
これからはもう少し範囲を広げて心地のいい暮らしを続けていくことにも目を向けて発信をしていこうと思っています。
読んでくださってありがとうございました。
この記事に関するお問い合わせは、こちらからお気軽にどうぞ。
もしくは、LINEからお問い合わせください。
