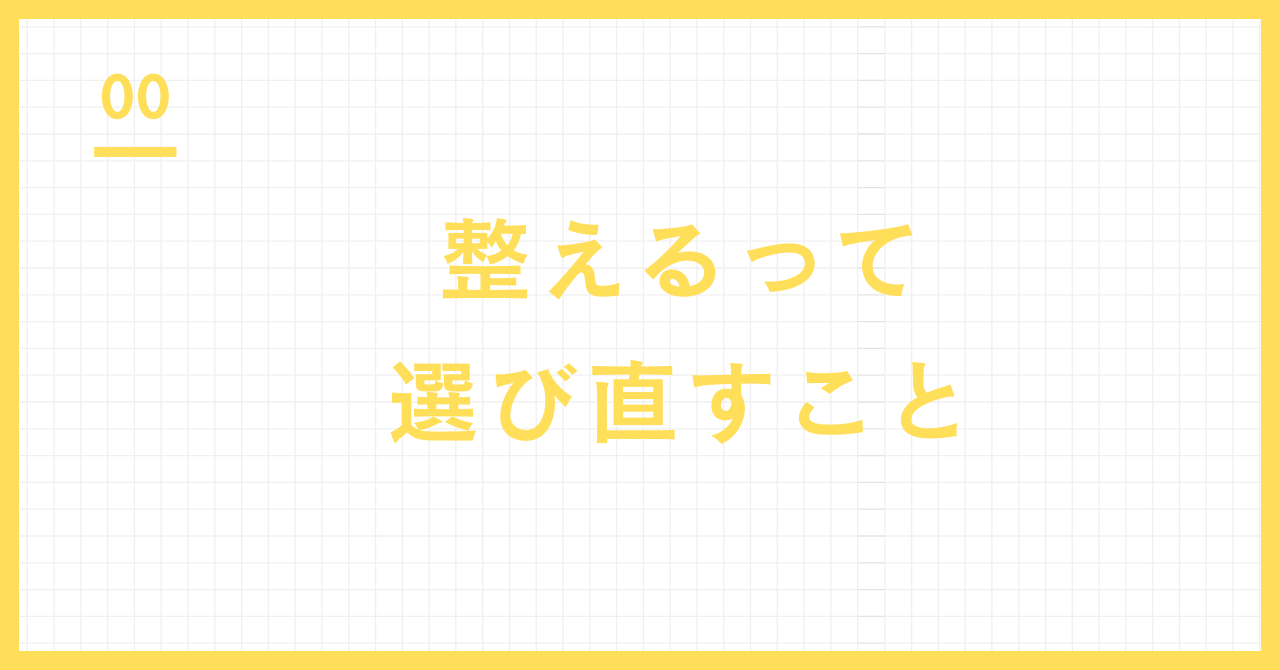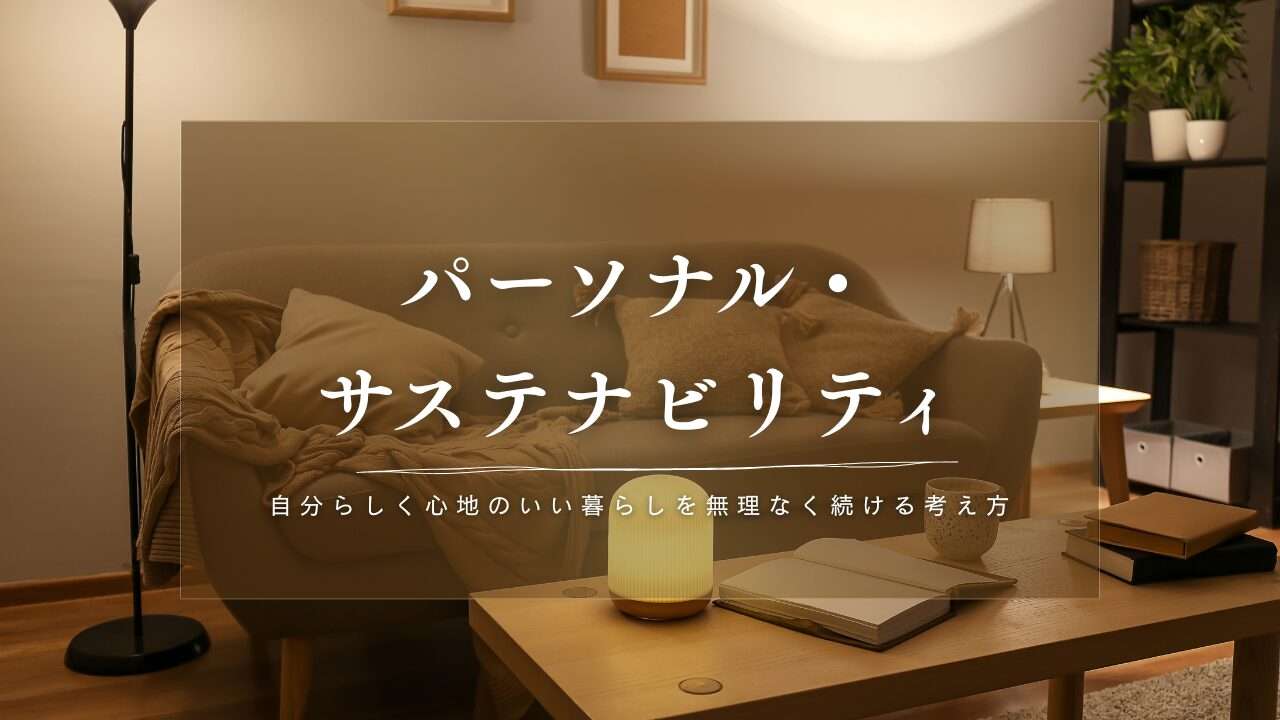
パーソナル・サステナビリティが必要な理由― “がんばる暮らし”は続かない
毎日を一生懸命こなしているのに、暮らしが整っていく実感がない。片づけてもすぐ散らかり、時間管理を学んでも余白が生まれない。
そんな行き詰まり感の背景には、できるだけたくさんのタスクをがんばることを前提にした生活設計があります。
人が日々使えるリソース(自分の持つ資源)は限られています。時間・体力・心のエネルギー・空間・お金が少しずつ削られると、暮らしをそのまま続けられる可能性は下がります。
短期的な根性や努力で整える方法は、ピークを越えた瞬間に崩れやすく、がんばり続ける暮らしは、長くは持ちません。
きれいに整った家や、完璧なスケジュールよりも、「無理せず、自分らしく心地よさが続く暮らし」を育てることが大切です。
そのために欠かせないのが、パーソナル・サステナビリティ(Personal Sustainability)。まずは自分自身の暮らしが「続けられる暮らし」になっているかを問い直します。
パーソナル・サステナビリティとは?
自分の暮らしを持続可能にする考え方
「サステナビリティ」と聞くと、多くの人が「環境問題」や「社会的な取り組み」を思い浮かべるかもしれません。
でも、ここでお話ししたいのは、もっと身近な──自分の暮らしそのものの持続可能性です。
私はこれを「パーソナル・サステナビリティ」と呼んでいます。
パーソナル・サステナビリティとは、
「今だけでなくこの先も自分らしく心地のいい暮らしが無理なく続けられるように、時間・エネルギー・心・空間・資源の使い方を自分の基準で選び、設計していくこと」。
1.自分の基準を取り戻す
SNSや雑誌には「理想の暮らし」「最先端/流行している物」があふれています。
誰かの正解や流行を追うほど、価値観、判断基準は自分から離れていきます。まずは「どう生きたいか」、「何を大切にしたいか」、「時間をどうやって使いたいのか」そんな問いを持つことで、選択の迷い、エネルギーの消耗が小さくなります。
2.整える=選び方を見直す
暮らしを整えるとは、物をやたらに減らすことでも、おすすめの収納グッズをそろえることでもありません。
暮らしを整えるとは「何を選び、何を持たないか」、自分の選び方を見直すこと。
3.内側から整える
見た目や仕組みより先に、自分の考え方やペースを整えます。パーソナルサステナビリティで大切なのは、外から足すより、内側から育てていく観点です。
内側から整える暮らし ―
選び方を変えることがサステナブルな生き方につながる
暮らしが変わらない最大の理由は、外側の改善ばかりが先行してしまい、それに内側の認識が伴っていないことです。
例えば、収納を増やしても、選び方が変わらなければまた同じように物が増えてしまい、すぐ満杯になります。
どれだけ時間管理術を学んでも、予定やタスクを詰めすぎて優先順位が曖昧なら、すぐ予定はいっぱい。いつまで経っても余裕は生まれません。
無理なく自分らしい心地よい暮らしを続ける土台は、外側の「形」ではなく、内側の「基準」から育てていく必要があります。
私は暮らしを変える本当の鍵は、「減らす」よりも「選び方を見直す」こと、つまり「整える=選び方を見直すこと」だと考えています。
物を減らすことや新しい仕組みを取り入れる前に、「今の自分に何が本当に必要なのか」「この選択は、未来の自分を疲弊させないか」という選び方そのものを見直すことがポイント。
それが、自分の暮らしを続ける力の土台になるのです。
価値観を見直す
今の自分にとっての大切・快適・安心・自信(自分を信頼/応援できること)を見直します。いつの間にか刷り込まれてしまっている過去の正解や、他者の期待から距離をとって、今と少し先の自分に合う判断軸をつくります。
現実を把握する
何に時間が消え、どこで心がすり減らされて、家の中はどこから散らかるのかを把握します。体感は事実とは異なることもあるので、数字や回数でも可視化し、ボトルネックを見つけます。
選び直す
価値観と現実を理解した上で入口(買う・始める)を意識的にを狭めることで、出口(手放す・やめる)を軽くします。足さない意識が大切です。
また、一気にやるより少しずつ進めます。選び方の見直しは単発の決断ではなく、習慣として繰り返す行為として捉えます。
時間・体力・心をすり減らさない暮らし方 ― 自分のリソースを守る視点
最近では整え方は「減らす」ことが主流で語られています。それに対し、パーソナルサステナビリティのコツはただ減らすではなく、むしろ「もっと増やす」よりは「減らさない」のさじ加減。無意識にリソースが失われていくのを防ぐと、身軽、気楽に過ごせるようになります。
時間
- スケジュールを詰め込みすぎない。
- 必ず毎日何もしない時間を確保する(「何もしない」は、スマホを見ることではありません。本当に何もしないことを指します)
- 移動や準備のバッファを前提に入れこんで計画する
- 何かを決める回数を減らすために、テンプレートを増やす
- 短時間の習慣を育てる
体力
- 回復(睡眠・休息)を優先する
- 日常生活に加えて、運動習慣をつくる
- 家事の動線は短くする
- 自分の体の状態を知る
心
- 人との比較や過剰な期待から距離を置く
- 評価されるための行動を減らし、自分に合う関係性を深める。
- タスク完了だけでなく、安心・納得・満足のサインを暮らしの評価軸に加える。
- 自分を責めず、自分を応援する
- 褒め、労わりは他者に求めないで自給自足する
持続可能な暮らしの仕組みづくり ― 意志ではなく仕組みで続ける
気合、根性、意志の力に頼る暮らしは、長くは続きません。「また続かなかった」「やる気が出ない」と自分を責める前に、暮らしを仕組みで回す視点を持つことが大切です。
仕組みとは「意識しなくても毎回同じ結果が得られる、自然に続けられる構造」のこと。
例えば
<アクション数を減らす例>
- 帰宅後すぐ荷物を置く定位置がある
- 朝の支度を最短ルートでできる動線
- スマホや財布の置き場所が固定されている
- オープン収納を活用する
<迷いを減らすマニュアル例>
- 書類の種類と対応を先に決めて一覧にしてまとめておく
- TPOに合わせた安心コーディネートを一覧にしておく
- 短時間で作れる家族みんな大好き献立をまとめておく
これらは、すべて暮らしを自動化する小さな仕組みです。「ちゃんとやる」ためではなく、「やらなくても散らからない」ために仕組みをつくるのです。
仕組みは、自分のリズムに合わせて微調整しながら育てていきます。一度つくって習慣になっていけば、暮らしのエネルギー消費がぐっと下がり、頑張らなくても自然とまわるようになります。
暮らしを支えるのは選び方を見直すことから生まれる
暮らしは一度整えたら終わりではありません。人の価値観や状況、体力、家族構成は時間とともに変化します。だからこそ、その時々で選び方を見直すことが大切です。
今の自分に合わないモノゴトを見直す
過去には役立った自分のこだわりやルール、価値観、習慣、さらにはそれらの基準で選んだ物が、逆に今は負担になることがあります。役割を終えた基準は、感謝して手放すようにしましょう。
小さく試して、小さく見直す
一気に変えたい気持ちもあると思いますが、一度に大改造してしまうと1つ1つの変化が暮らしに与える影響がすくいとれません。
それよりも、小さな実験と微調整をすることで、無理なく見直しを進めます。
まずは自分の内側から。そして、方向性が見いだせたらそれに合わせて家の中での行動、物、動線、配置を見直していきます。
未来基準で俯瞰して考える
今、私たちが何をどう選ぶかは、未来の自分が払うコストを決めます。
整えることの本質は「完璧な状態を維持すること」ではなく、「変化に合わせて暮らしを再構築していくこと」。
暮らしの中で生まれる小さな違和感を見逃さず、その都度「今の自分に合うか?」、「これを選んだら、その先には何があるのか?」を問い続けることで、自分らしく続けられる暮らしが育っていきます。
まとめ ― パーソナル・サステナビリティを考えながら暮らしの土台を育てる
パーソナル・サステナビリティ(Personal Sustainability)は、特別な人だけの考え方でも、環境保護の話でもありません。自分らしく心地のいい暮らしの持続可能性を高める、実践的な生活設計です。
自分の基準を取り戻し、「整える=選び方を見直す」という視点で、内側から整える。時間・体力・心・空間・お金というリソースを減らさない設計に切り替え、意志ではなく仕組みで続ける。そして変化に合わせて選び方を見直す力を育てる。
こうして土台をつくっていけば、がんばらなくても続く暮らしに近づきます。自分の基準に合わせて選ぶ力は、自分を幸せにする力です。それは外から、他者から与えられるものではありません。
「この暮らしは、私にとって無理なく続けられるだろうか?」
この問いを合図に、今日から自分の選び方の見直しを始めてみてください。
追記:2025年10月からnoteにて毎日1テーマで「パーソナル・サステナビリティ」や「サステナブルな暮らし」(こちらは環境関係につながる、消費者としてできることについて)に関わる、読者の方と価値観や考え方を見直すきっかけになるような投稿をしています。
ご興味を持っていただけましたら、あわせてご覧ください。
URL: https://note.com/optlife
この記事に関するお問い合わせは、こちらからお気軽にどうぞ。
もしくは、LINEからお問い合わせください。